


今年の審査では、カッティングシートの意外な使い方と、そのねらいと効果がよく合致している作品に評価が集まった。グランプリの「明日は遊園地へ行こうね」は、街角に設置される壁画のようなアート作品だが、カッティングシートを、まるで漫画家が用いるスクリーントーンのような多彩な陰影や調子を表現する手法として用いている点に独創性があった。漫画の背景画のようなタッチが、街頭で遭遇するスケールの絵として展開されていた。
準グランプリの「studio souriant」は、写真スタジオと思しき施設の入り口に赤い透明なカッティングシートをぴったりと隙間なく貼り込まれたものだ。昼は差し込む光を赤く呼び込み、夜は内部から外へと赤い光が洩れ出す。建築の一箇所に半透明の赤を集約した視点に冴えを感じた。「大成建設関西支店ビル グリーン・リニューアルZEB」は、年輪のような円の積層をモチーフとしたヴィジュアルを、サイン表現の背景として展開したものだ。半透明の存在感を意識したサインは、効果的に環境に溶け込んでいるように感じられた。「衝突防止」サインは、手描きの描線を心地よいタッチのストロークで描いたもので、空間に人工的なノイズのないレイヤーを生み出していた。
優秀賞の「Sony Park展 KYOTO」は、音楽をテーマに、工場内を誘導するパターン化された動線表現と、バスストップのようなスタンドサイン、そして随所に配される歌詞による構成に要点を押さえた秀逸を感じた。「Constellation.」はバー空間の光を、カッティングシートで巧みに演出したものだった。昼は外光、夜は室内の灯りが、鏡面のようなカウンターに映り込む。酒ボトルやグラスを透過・反射する光がカッティングシートで巧みに制御されていた。「静かな詩のように」は、美術館として用いられている建築の、アルミサッシのガラス面に詩を展開したものだ。意味と同時に物質として、空間に展開された言葉のリアリティに惹かれるものがあった。「ニセコ町役場」のサインは引き違いガラスの扉の運動によって絵が重なる、微かなウイットにほだされた。「安平町立早来学園」、は震災で統合を余儀なくされた小中学校に、復興を支える「手」のビジュアルを配するというもので、手描きの文字と共に、心の微妙な振幅を伝える優しいデザインであった。
いずれも、常套的なカッティングシートの利用法ではない、素材の可能性を広げていく、独自の視点を持つ作品が賞に選出された。
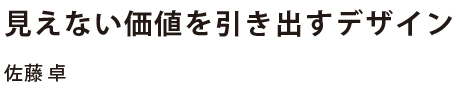

カッティングシートは、貼るだけでその空間を明るくしたり楽しくしたり、新たな機能を持たせたり、貼り替えることによって変化をつくったり、空間の視覚的な可能性を無限に広げてくれる素材だ。その可能性を探るのがこのCSデザイン賞であるため、今までにない新しい提案性があるものに賞が与えられる。この賞の意義がそこにあるのだから当然だ。しかし、普段の生活でそのような提案性の強いものがあり過ぎると、ノイズにもなりかねない。生活の周辺のほとんどが無意識の中に入ってくれればいいのであって、そこここに主張が強いものがあれば心地よくはないだろう。ゆえに、新規性がなくても普通で心地よい使い方が実は多くあるはずだ。シートを使っているのかどうかも言われなければわからない使い方もあるだろう。そしてそのような控えめな使用例は、そもそもこのようなところにはあまり出品されてこない。この審査では、毎回ハッと思わせる作品に出会えることを期待している自分に気付かされるが、その反面、環境に馴染んでいるなんでもない使い方にも出会いたいという想いが常にある。このような複雑な心境を抱えながら今年の審査にも参加してグランプリにはまたユニークな作品が選ばれた。そして素直に面白いと思った。まるで漫画に使うスクリーントーンのような使い方は、綺麗に貼って美しく見せる通常の使い方とは全く異なっている。シートの上にさらに手描きが施されていたり、その自由な使い方には新しい可能性を感じることができた。
このように実際に審査に入ると、使い方にインパクトがあるものに注目することになるが、どこかで、何気ないけれども今まで例がない使い方、つまり説明を受けないとわからないくらい微妙な使い方に出会いたいと思っている自分がいる。意識させるものではなく、感覚に訴えかけるものだ。社会があまりにも意味を求める脳化社会に陥っていることへの反動なのかもしれない。そのような状況にあって、被膜のようなこのカッティングシートのデリケートな可能性が、今後もこのCSデザイン賞で発見されることに期待したい。
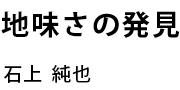

世の中の多くのものはより簡便な技法へと収斂していく傾向がある。しかし、過去の技術がもつ独特の雰囲気と魅力に惹かれてしまうというのも、一方で事実である。人は失われつつある状況のなかで、初めてその価値に気がつくのかもしれない。
カッティングシートも、塗料よりも簡便だということで世の中に普及していった。それを踏まえて上記と同様の意味において、手数が多く手垢の残る塗装技術に、逆に温かみのような感情を抱いてしまう。もちろん、カッティングシート自体、無数の表現を生み出す可能性を秘めているし、実際、想像もつかないような利用方法に驚くことも多い。しかし、それでもその多くは従来のカッティングシートの手法の延長であって、作業の難易度を度外視すれば、塗装によっても代替できる方法であるような気がする。カッティングシートによって失われた手作業で塗ることで生まれる人の痕跡としての質感を取り戻すものではない。
このような状況の中で、今回のグランプリである「明日は遊園地へ行こうね」は、既存のカッティングシートの価値観を大きく変える作品だ。漫画のひとコマを拡大し巨大絵画にするというものである。漫画とはなにかという哲学的な問いとともに、根本的な意味における漫画性を探求することで、漫画を芸術の次元まで昇華させることを意図している。その探求のひとつとして、漫画業界で失われつつあるスクリーントーンの技法に着目している。衰退の理由は、高価で手間のかかるスクリーントーンよりも、作画をデジタル化した方が安価で利便性がよいからである。この構図は、カッティングシートと塗装との関係に酷似している。
作者は、漫画のひとコマを巨大化する過程で、市販のスクリーントーンではなく、カッティングシートでトーンを自作するに至った。既存のスクリーントーンでは、漫画をスケールアップするという目的に適合しなかったからだ。既存のスクリーントーンと同じ役割を果たすものとしてカッティングシートを利用し、カッティングシート自体をスクリーントーンと同等の画材に置き換えている。そのことによって、過去の漫画がもつ技術的価値を芸術のレベルで復興させようとしているのである。
塗装という技法がもつ人の温もりを恋しく思いつつ、大量のカッティングシートが利用されている現代において、スクリーントーンの代わりにカッティングシートを利用することによって、漫画が本来持っていた人の手の跡と温もりを再現する。これは、カッティングシートの価値観を別の次元に転換することになるのではないか。
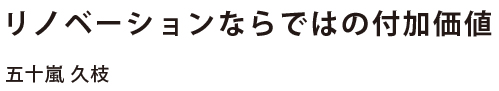

今年は、マンガ制作法を用いた表現がグランプリに輝いた。マンガと言われても、すぐにはピンとこなかった。が、スクリーントーンの貼り方には妙に懐かしさが感じられて、そこにばかり気を取られていた。通常のマンガには必ず描かれている、あの特徴的な吹き出しセリフや擬音はこのマンガには描かれていない。巨大な1枚は、通常手にするマンガのスケールを逸脱している。その大きな一枚にいくつものストーリー性のある場面が散在し、俯瞰的に描かれた現代の屏風絵のように、見る側の視線を次次へと動かしてしまう。しかしマンガであって、それは1枚の絵とは言わないのだ。面白い。スクリーントーンの技法をカッティングシートでオリジナルを作成し、重ねて貼り込む層の重なりの厚みが動きや陰影の世界観を表している。上からさらに描き足されたインクのタッチが、作者の制作のタイミングを想像させ、言葉を使わないマンガとストーリーと時間の対話を次次と享受する。何とも面白い感覚だと思った。詳細な加工に対応するカッティングシートの表現がまた活かされ、また拡がったように感じられた。
準グランプリのサイン計画では、「一本の大木の年輪」から各階表示を年輪の切り取りから表現をするという建設会社らしく大胆なモチーフを選択されている。それは2050年のカーボンニュートラル実現に向けた強い意志と、ZEB(ゼロ・エネルギー・ビル)に目標を掲げる表現として相応しい。1Fエントランスに設置された年輪の芯から始まり、円弧の緩急によって階層の上下を認識されるように計画している。上層階では、大きく緩やかに伸びた円弧は清流の流れ、宇宙の起動のようにも感じられるのではないかと思った。このサインを目にする人々にZEB意識を無理なく働きかけるであろう。モノトーングラフィックは動きを感じさせ、記号であるかのように見えることも想像力をわきたたせるように感じていた。
優秀賞のConstellation.は、古い建造物の特徴的な窓の形状を活かした、ガラス全面にセプテットフィルムを貼り込み、そのオパールの光に訪れる顧客は包まれるのであろう。古い建造物ならではの厚すぎる壁の奥行きが、よりセプテットフィルムの効果を引き出している。そしてその効果はより現実感を喪失させているのではないかと。昼と夜、部屋の内と外、刻々と過ぎていく時間と共に光を変様させ、日常の景色をおぼろげにするというオパールの光を魅了する。非日常を堪能するためにいつか訪れようと、そう思わせられるビジュアルである。
2024年今年も発見のある審査会となった。どこか懐かしい、現在と過去の時間が交差する空気や相反するものたちが混ざりあう気配が漂っている。


今回のグランプリ「明日は遊園地へ行こうね」は、マンガの作画スタイルを用いて、校庭での情景を描いたアート作品だ。赤い帽子の少年が地面になにか大きな鳥のような絵を描いているように見えるが、詳しくはわからない。前後のストーリーは不明なまま、鑑賞者は唐突にマンガのなかの一場面に送り込まれる。校舎のよごれた壁や、金網のフェンスの描写に、寂しいような懐かしいような気分が漂っている。この作品では、カッティングシートがマンガ制作のスクリーントーンの代わりに画材のひとつとして用いられている。もともとは大きな面積を均質に仕上げるのに適したシート素材が、ここでは重ねて貼られたり、上から別の画材の描線が加えられたりしながら、細かい凹凸のテクスチャーを生み出すのに一役買っている。マンガの業界では作画のデジタル化が進んで、実際にスクリーントーンを切って貼ることはだんだん少なくなっているようだが、この作者は逆に手作業の積み重ねによる微妙なテクスチャーに表現の拠り所を見出しているのかもしれない。審査会でこの作品に惹かれた直接的な理由は、描かれた場面の魅力と、カッティングシートを巨大なスクリーントーンとした使用方法の斬新さということになるが、しかし審査のあと時間が経って振り返ってみると、単なる使用方法のアイデアというよりも、手の痕跡としての微妙なテクスチャーがもつ価値が、これからのデザインのひとつの方向のヒントを示しているようにも思えた。準グランプリの「studio souriant」の鮮烈な赤い透過光も忘れがたい。エントランスのガラス面に赤い透明シートを貼ったシンプルなデザインが、モノトーンのスタジオの外観にも内部空間にも大きな効果を生んでいる。同じく準グランプリの「衝突防止」は、アーティストによる美しいドローイングの線が、単なるガラス面の衝突防止の役割を越えて空間の質を高めている。優秀賞の「ニセコ町役場」と「安平町立早来学園」は同じデザイナーによるものだが、どちらも公共空間のなかのグラフィックデザインとして気持ちのよい作品だ。優しさと工夫のある発想を生かしながら、仕上げに際して甘すぎずベタつかないところで留めたデザインの判断が優れていると思う。